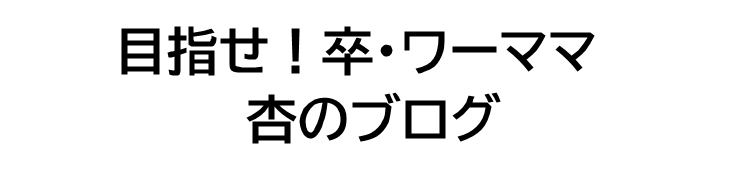私が働き続けてきた背景には、祖母、母、そして私自身という三世代の女性の姿があります。
祖母は、祖父が他界したあと、母を育てるために働いていました。仕事を持つ祖母は、身だしなみにも気を配り、社交的で美しい人でした。祖母のすべてを知っていたわけではありませんが、幼い私にとって、その姿は強く心に残る憧れでした。
母は国家資格を持つ、聡明で明るい人です。けれど、出産と同時に専業主婦となり、その後再びフルタイムで働くことはありませんでした。どこかで「男は外・女は中」という価値観に縛られていたのだと思います。母は世の中の流れに逆らうことは選ばなかったのです。家庭を支え続けた母の人生にも、尊さがあると今は思えますが、当時の私は、そんな母の姿に少し疑問を抱いていました。
そして私は、男女同じ教育を受けてきたにもかかわらず「女性だから」という理由で補助的な役割に回されることに納得がいきませんでした。だからこそ、就職活動のときから「男女同待遇」の会社を選び、妊娠や出産で仕事を辞めるという選択肢は、最初から考えていませんでした。
もちろん、仕事には嫌なこともたくさんあります。でも、それ以上に学ぶことが多く、やりがいや楽しさもあります。
ハーバード大学医学部の内田舞准教授が、出産前に昇進された際、上司から「どんなにゆっくり走っていてもいい。でも馬から降りてはいけない」と言われたというエピソードを知ったとき、深く共感しました。私も、責任のある仕事内容やポジションを維持し続けるためには、どんなことがあっても仕事を辞めてはいけないと思っていたからです。だから私も「馬から降りない」ことを選びました。
今の時代、出産や育児を経てから再び正社員として働き始める方もたくさんいます。それを叶える努力は素晴らしいことだと思います。でも、私は自分にあまりある頭脳や才能があるとは思えなかったので「一度辞めてしまったら、戻るのは難しいかもしれない」と考えていました。制度の整った企業を選び、産休・育休、そして育児時短制度を活用しながら働き続けてきました。
とはいえ、子どもが赤ちゃんだった頃の私は「ゆっくり馬に乗っている」どころか、がむしゃらに走り続けていたように思います。
口癖は「早く早く!」で、子どもにも「早く靴を履いて」「早く着替えて」「早く寝て」と、急かしてばかりだった気がします。もっと心に余裕をもって接することができたのでは……と、今になって思うこともあります。今の社会には、そんな“ゆっくり進む”ことを受け入れる寛容さも、少しずつ育ってきているのではないでしょうか。
通勤途中で見かける光景に、道路で泣き出した子どもと、必死に叱るお母さんがいます。あの姿は、かつての自分のようでもあり、見るたびに心が痛みます。「行きたくない日だってあるよね。一緒に少し散歩しようか」――そんなふうに声をかける余裕は、当時の私にはありませんでした。だからこそ、今、そんなお母さんに心の中でそっとエールを送っています。「あと10分、一緒にいてあげたら、きっと落ち着くかもしれないよ」と。
先日、娘に「小さいころに、いつもいつも急かしてごめんね」と伝えました。娘は「そうだっけ?」と受け入れてくれてました。今のように週2-3回でも在宅勤務ができたら、だいぶ変わってただろうな、とは思います。子どもたちが手のかからない歳になっても、それでも在宅勤務は家事もはかどり有難いものです。
子育ては、もはや女性だけのものではありません。保育園のお迎えにダッシュするのも、女性だけの役目ではなくなってきました。ダッシュするのも夫婦でシェアし、そのうえ在宅勤務を間に挟むと改善しそうですよね。あと数年で就職する娘が家族を持つ頃には、もっと心に余裕をもって子どもを見守れる世の中になるといいな、と思っています。そうして、もっと苦労することなく仕事が続けられる社会になるといいですよね。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
これからも、少しずつでも誰もが働きやすい社会に近づいていきますように。